 苦みは文化の集大成
苦みは文化の集大成
もしも私たちの食卓から苦みが無くなったら……これは一大事です。
想像してみてください。愛すべきお茶(カフェイン、タンニン、カテキンなど)はもちろん、チョコレートのカカオ(テオブロミンなど)やコーヒー(クロロゲン酸類など)、ビールのホップ(ルプリンなど)をはじめとする、これら苦み成分を利用した飲み物や食べ物が存在しない世界は、大人には物足りないのではないでしょうか?
人類は、これら苦みのある物質を、気晴らしや癒やしの嗜好品に、医学の発展や日々の生活の健康維持に、また食事のアクセントや刺激として利用してきました。
苦みを扱う知恵や知識は、実は私たちの文化のエッセンスであり、集大成なのです。
 植物の毒とお茶の伝説
植物の毒とお茶の伝説
苦みはヒトの基本となる5つの味覚=甘み、酸味、塩味、うまみに含まれていますが、その存在は独特です。
舌の上に強い苦み物質を乗せると、その刺激を受けた脳は嫌悪感を生み出し、口はへの字に結ばれ、鼻にはしわが寄り、舌は口の外に突き出されます。
これはそもそも「苦み」が、生物にとって毒を体に入れないための危険信号として存在していたことに由来しています。
原始的な生物、例えば5億年前に地球上に登場したイソギンチャクは、消化管に苦み=毒を感知すると吐き出します。同様に赤ちゃんや幼児が、苦みを持つ物質や食べ物を口にすると反射的に吐き出すのも、この体の警報が機能するためです。
さて、世の中の苦みのある物質の多くは、植物によって生み出されています。植物は感染症の微生物を殺す毒として、また捕食者から身を守るため、その身に苦みを持つ化合物を生成するように、無数ともいえる種類に進化しました。
10万年前にアフリカを出発した我々の祖先たちは、あらゆる土地の様々な植物を口に入れてみることで、この植物の苦み=毒をも飼いならし、学び、コントロールし、食品や薬物として利用する方法を発見してきました。
これは古代中国の医学と農業の神「神農」の伝説を思い出させます。神農は無数の植物を舐めることで判別し、その利用法を人々に伝達しました。また自らの体に溜まった植物の毒素を、1日の終わりにお茶で解毒した、喫茶の習慣の始祖としても知られています。
 苦みを活用する
苦みを活用する
最新のヒトの分子生物学的な解析では、甘み=糖や、うまみ=アミノ酸を感じる受容体が2〜3種類程度であるのに対して、苦みの受容体は26種類あることがわかっています。これは我々の体が、数億年の時間をかけて体内のセンサーを組み合わせ、千種類以上の苦み物質を受容するように進化してきたことを証明しています。単純な構造の甘みやうまみと比較して、自然界の苦みや毒の種類は大変に多く、機能も複雑です。
しかし、お茶の苦みが心地よい休息の時間を与えてくれるように、季節の野菜やハーブの刺激が料理のおいしいアクセントとなるように、植物の苦みや毒は、適量であれば、体にとって良い効果をもたらしてくれます。
七草粥の習慣など、春に山菜や野草を摂取するのは、冬の間に停滞していた体の機能を植物の苦みで活性化させるため。真夏にゴーヤなどの夏野菜がおいしく感じられるのも、適度な苦みが胃を刺激し、消化酵素や胃酸の分泌を促してくれるためです。
ここ十数年、コンピューターや分析機器のコストダウンと進化によって、様々な植物の有機化合物(アルカロイド)の成分の分析が急速に進められています。
世界各地に伝わるおばあちゃんの知恵、魔女や呪術師の植物を使ったおまじないなど、主に口伝で利用法が伝わってきたローカルなハーブ類まで、その機能が調査される機会が増えています。これら植物の苦み成分を、正しく知り、利用することは、実に21世紀的な課題なのです。
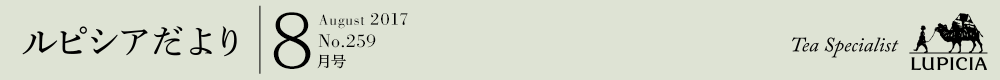




ジョン マッケイド著、中里京子訳(2016)『おいしさの人類史 人類初のひと噛みから「うまみ革命」まで』、河出書房新社
ペニー・ルクーター/ジェイ・バーレサン著、小林力訳(2011)『スパイス、爆薬、医薬品 世界史を変えた17の化学物質』、中央公論新社